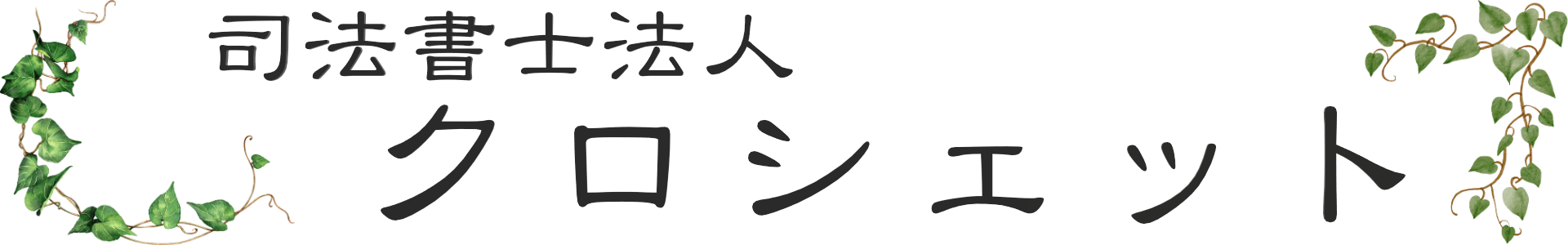遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人(=亡くなられた方)から相続した財産を、相続人たちの間で分けるためにする話し合いのことです。
この話し合いにおいて「どの相続人が、どの財産を、どんな割合で相続するのか」ということを具体的に決定することになります。
遺産分割協議の準備
- 遺言書の有無を確認する。
- 相続人を調査・確定する。
- 遺産分割協議に参加することになる法定相続人を調査し、確定させます。
- 包括受遺者がいる場合は、その方も遺産分割協議に参加する必要があります。
- 相続財産を調査・確定する。
- 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。
- 遺産分割協議の結果にしたがい、必要な手続きをする。
相続人の調査
遺産分割協議は、必ず相続人の全員によって行わなければなりません。
たとえ、長いあいだ付き合いが途絶えている相続人であっても、協議には参加する必要があります。
もしもお一人でも遺産分割協議に参加しなかった相続人がいた場合には、その遺産分割協議は無効となります。
そのため、話し合いの当事者となる相続人は誰であるか、相続人の全員が揃っているか、協議を開始する前に調査を行ってください。
なお、相続放棄を希望する相続人がいる場合には、必要な手続きを取った上で、その方は話し合いから外れることになります。
遺産分割の方法
遺産分割の方法として、以下のような方法があります。
現物分割
「現物分割」とは、個々の相続財産を、そのままの形や性質で、分配する方法です。
例えば、遺産として「A不動産」と「B不動産」がある場合に、「A不動産」を長男が相続し、「B不動産」を次男が相続する、という方法です。
また、例えば遺産が「C土地」である場合に、その土地を2つに切り分けて(=分筆して)、それぞれの土地を長男・次男が相続することも現物分割になります。
| メリット | 対象となる財産をお一人が相続するため、シンプルで分かりやすく、売却や評価、代償金の支払いなどの手間がかかりません。 |
| デメリット | 法定相続分などのある一定の割合をもって、正確に分割することが難しい方法です。 |
代償分割
「代償分割」とは、ある相続人が、自己の法定相続分を超えて財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払う方法です。
例えば、遺産として「D不動産(価額4,000万円)」がある場合に、長男がそのD不動産をすべて相続し、次男に代償金として、2,000万円を支払うという方法です。
| メリット | 対象となる財産を、分筆したり売却したりする必要がなく、財産をそれまでの形で残すことができます。 それぞれの相続人が取得する財産の価額を一定にすることができ、公平な相続を実現するすることができます。 |
| デメリット | 取得する相続財産によっては、代償金が高額となることがあるため、相続財産を取得することになる相続人にとっては金銭的な負担が大きくなりがちです。 また、代償金が支払われないリスクが残ります。 |
換価分割
「換価分割」とは、遺産を売却することで現金に換えてから、その現金を分割する方法です。
例えば、遺産として「E不動産」がある場合に、その不動産を売却した上で、売却代金を相続人の間で分配する方法です。
| メリット | それぞれの相続人が取得する財産の価額を一定にすることができ、公平な相続を実現するすることができます。 |
| デメリット | 売却の手間や時間がかかるほか、財産がそれまでの形としては残らないことになります。 |
共有分割
「共有分割」とは、ある相続財産を複数の相続人が共有する方法です。
例えば、遺産として「F不動産」がある場合に、その不動産を長男・次男が2分の1ずつの持分を取得して、共有する方法です。
| メリット | それぞれの相続人が取得する財産の価額を一定にすることができ、公平な相続を実現するすることができます。 |
| デメリット | 共有者について、さらに次の相続が発生すると、権利が細分化・複雑化していくことになります。 利用や売却が困難となる可能性もあります。 |
遺産分割協議の注意点
- 遺産分割をする前に、例えば相続人のお一人が亡くなってしまった場合は、さらにその相続人が遺産分割協議に参賀する必要があります。
- 認知症などにより認知能力が不十分な相続人は、遺産分割協議に参加することができません。
このような相続人がいる場合に遺産分割協議をするには、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、選ばれた成年後見人が代わりに協議に参加することになります。 - 「未成年の子」と「その親」がともに相続人となっている場合、親はその子を代理して遺産分割協議に参加することはできません。
また、相続人の中に「成年被後見人」と「成年後見人」がいる場合も、「成年後見人」は後見人の立場として遺産分割協議に参加することができません。
これらの場合は、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、選ばれた特別代理人が代わりに協議に参加することになります。